AIは人間を超えるか(その2)。
- 熊澤剛

- 2025年9月2日
- 読了時間: 3分

前回に引き続き、NHKの「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?(びっくりはてな)」から受けた私のインスピレーションを書き綴って行きます。
対話型AIの能力は、知能の内の「予測能力」であるという東京大学大学院の松尾教授の言葉をご紹介しました。
AIは膨大なデータからパターンを学習し、次に続く可能性が高い言葉や情報を予測して生成します。
しかしながら、もっともらしい虚偽=ハルシネーションを生む可能性を含んでいます。
また、AIには身体性がない為、処理された情報を自ら体験することで、確認したり補正したりすることもできません。
それでは、AIは人間を超えることはないのでしょうか?
AIが自己フィードバックによる改良を繰り返すことによって、人間を上回る知性が誕生する=シンギュラリティー(技術的特異点)に到達するという仮説は、ただの空想上の産物でしかないのでしょうか?
この答えは、知能の定義により変わるものと考えます。
人間が持つ様々な能力の総体としてのAIは、身体性を獲得しない限りは難しいものとなります。
こうした能力を持つAIは、「汎用人工知能(Artificial General Intelligence:AGI)」と名付けられいています。
これに対して現在の対話型や生成型AIなどのAIは、「特化型AI(Nallow AI)」と呼ばれています。
番組では、初めて見るキッチンのセットで、コーヒーを淹れるという作業を例示していました。
自分でコーヒーを淹れたことがある人であれば、自分の家以外であっても、コーヒーを淹れる為に何が必要で、それはキッチンのどの辺にあって、どういう順番で行うべきかが大体わかります。
これらの人間にとっては何気ない一連の動作は、AGIが実現されなければ不可能なのです。
Nallow AIではコーヒーを淹れる手順を教えることはできても、自律的に状況判断を行い、この一連の動作を行うことは困難です。
一方で、知能の一部である予測能力に特化すれば、既に対話型AIは人間を超えつつあるのではないでしょうか?
見聞きできる情報であれば、膨大な量を学習し続けているAIに人間の勝ち目はありません。
文章の要約やプログラムの生成など、AIは既に人間の数万倍の速さで正確にやってのけます。
まとめると、人間の全ての能力を超えるAGIの実現には身体性が不可欠な一方、人間を補完する為のNallow AIにおいては、身体性は不要なのではないかというのが前回の記事の問いかけの答えとなります。
一方で、このAIに身体性は不要とする考え方は、「意識や知能は物質的な身体に依存しない」という立場に基づいています。
知能を情報処理のアルゴリズムと見なし、物理的な身体がなくても、計算機上でのシンボル操作だけで実現できるというものです。
う~ん、ちょっときな臭くありませんか?
これは前回提示した「ホワイトヘッドの具体化誤謬」を内包しているのでは?というのが私の考えです。
続きは次回のブログにて。



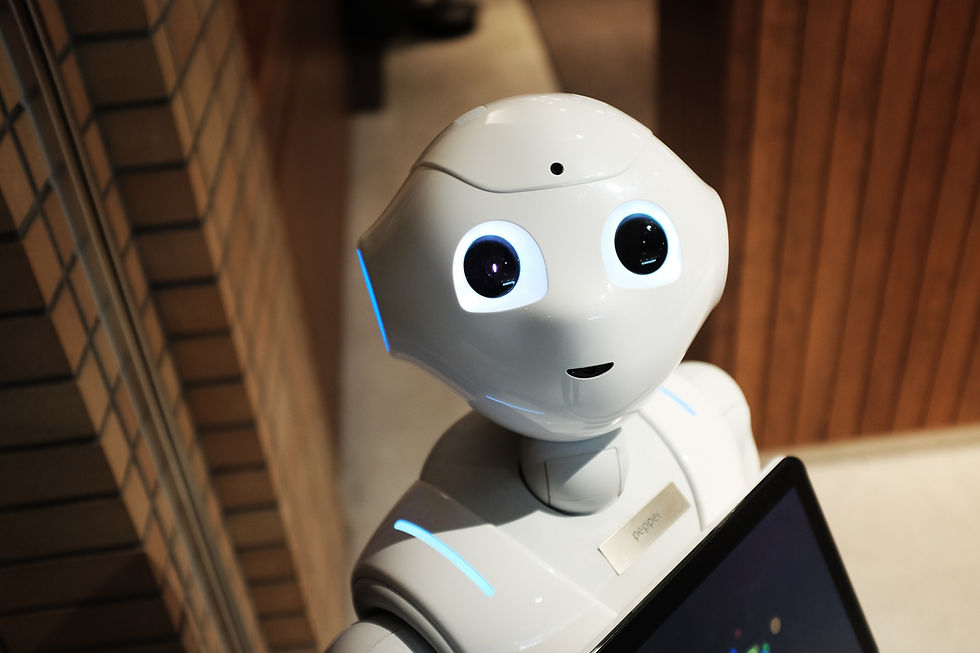
コメント