AIは人間を超えるか(その3)。
- 熊澤剛

- 2025年10月1日
- 読了時間: 3分

前回、AIが人間を超えるかという問いについて、こんな話をしましたね。
**全部の能力を合わせたAI(AGI)**は、まだ遠い未来の話。
**特定の能力に特化したAI(対話型AIなど)**は、すでに予測などの分野で人間を超え始めています。
そして、人間らしい知性(AGI)には、体を持つこと、つまり身体性が絶対に必要なようだ、という話もしました。一方で、今のAIの主流(計算主義)は、「知性は単なるプログラム(ソフト)、体は器(ハード)で、別々に考えられる」という立場です。
しかし、この「知性はソフトだけ」という考え方には、哲学者ホワイトヘッドが指摘した「具体化誤謬」という、大きな落とし穴があるんです。
AIの賢さは「地図」にすぎない
AIがどうやって賢さを手に入れ、私たちに「知的な回答」を提供しているかを見てみましょう。
1. 現実を「切り取る」(抽象化)
まず、AIは知能というめちゃくちゃ複雑な現実を、とてもシンプルな形に切り取ります。
人間の知性は、感情、身体の動き、経験、環境との関わりなど、ごちゃ混ぜになってできています。しかし、AIはそこから**「計算できる部分」「論理で処理できるシンボル」だけを抜き出し、アルゴリズムという**モデル(地図)**に変換します。**これは、複雑な森(現実の知性)を、道路と建物だけが描かれたシンプルな地図(アルゴリズム)にすることに似ています。
2. 地図を「現実」と誤解する(具体化誤謬)
AIが私たちに出してくる答えは、この**「計算可能な地図」**の結果です。コンピューターの得意分野ですから、その処理スピードや効率性は、生身の人間が太刀打ちできるレベルではありません。
問題は、多くの人がこの**「地図」をもって、「これが知性のすべて**だ」と信じてしまうことです。
具体化誤謬とは、まさにこの間違いです。
**抽象的な概念やモデル(地図)**を、まるでそれが具体的な現実そのもの(森)であるかのように扱ってしまう過ちです。
AIの計算主義が犯しているかもしれない誤謬は、「知性は単なるアルゴリズム(抽象概念)だ」と断言することで、身体性や環境との関わりといった、現実の知性にとって本質的な要素を切り捨ててしまう点にあります。
知性から失われた「意味」と「プロセス」
この誤謬のせいで、AIの賢さには決定的な何かが欠けている可能性があります。
「意味」の欠落: AIは文字(シンボル)を上手に操作できますが、その文字が指し示す本当の意味は、体を使って世界に触れたり、感じたりする経験から生まれます。体を持たないAIがシンボル操作だけで「賢い」と見なされるのは、知性の具体的な土台である「意味」を無視し、抽象的な操作だけを過大評価していることになります。
「流れ」の無視: ホワイトヘッドは、世界は常に変化し続ける**「プロセス(流れ)」であり、固定された「モノ(実体)」ではないと考えました。知性を、体や環境から切り離された「アルゴリズム」という固定されたモノとして捉えることは、知性が持つ身体と環境が織りなす生き生きとした動的な「流れ」**を見落とすことになります。
AIは、現実から最も効率の良い部分を抜き出し、賢さを提供しています。しかし、その「効率」と引き換えに、知性の本質を失っているかもしれない。
だからこそ、AIが出した結論であれ、誰かの発言であれ、鵜呑みにせず、「これは現実のどの側面を切り取った結果なのだろう?」と立ち止まって考えることが、ますます大切になっているのですね。
※今回の記事はGeminiに何回か推敲してもらいました。わかりやすいですよね・・・


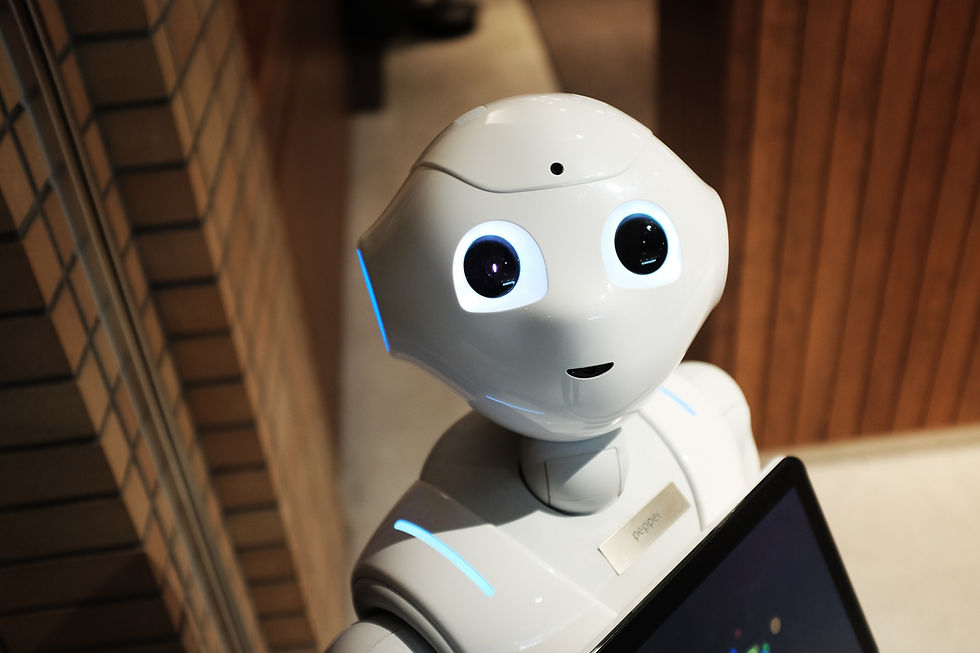

コメント