コミュニケーションと心理的安全性(その3)
- 熊澤剛

- 2025年4月1日
- 読了時間: 2分

「コミュニケーションの効率化は心理的安全性を損なうのか?」
前回の記事で心理的安全性の定義について説明しましたので、今回はコミュニケーションについて述べたいと思います。
いわゆる懇親会などを除いた、組織のコミュニケーションの役割は、直接的に3つだと考えています。
1つは情報伝達。
組織運営に必要な情報を組織内外の関係者に伝達し、共有する為のコミュニケーションです。
2つは意思決定。
組織内外の情報を収集・分析し、問題解決や意思決定を支援する為のコミュニケーションです。
3つは思考拡大。
私の造語で恐縮なのですが、意見交換や議論を行い、発想の飛躍や思考の拡大を促進する為のコミュニケーションです。
上記の役割が上手く機能した場合、相互理解や意思疎通、信頼関係の構築、更には組織文化の醸成などの間接的な効果が生じるものと考えています。
そうだとすれば、今回テーマとしている心理的安全性においては、どのコミュニケーションが行われるかは問題ではなく、どれであれコミュニケーションが上手く行くことのみが大切だということがお分かりいただけるかと思います。
メンバーがそれぞれのコミュニケーションの中で、無知、無能、邪魔、ネガティブだと思われることなく、自信や信念を持って発言できること。
これにより、心理的安全性が強化され、そのことが相互理解や信頼関係の構築に繋がり、やがてはそうした組織文化が醸成されるに至ることが可能だと信じています。
では、上手く行くコミュニケーションだったら、むしろ増やすべきなのか?合理化すべきではないのではないか?
次回はいよいよメインテーマに結論を出したいと思います。



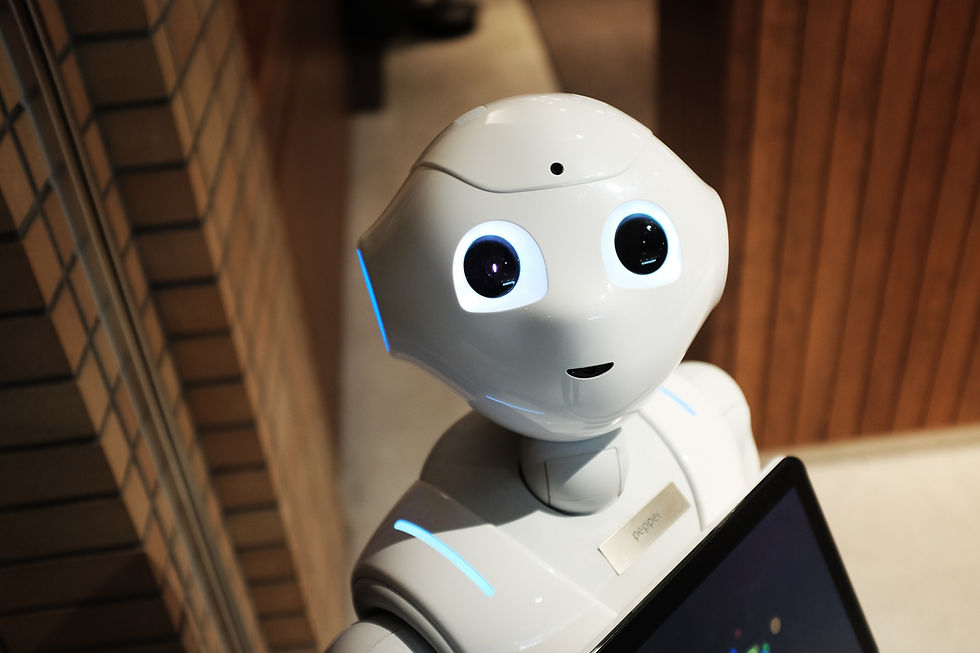
コメント