コミュニケーションと心理的安全性(その4)
- 熊澤剛

- 2025年5月1日
- 読了時間: 3分

「コミュニケーションの効率化は心理的安全性を損なうのか?」
前回の記事で、コミュニケーションはその役割によらず、上手く行くことが肝要であるとお伝えしました。
そうであれば、上手く行くコミュニケーションを効率化してしまうと、心理的安全性が損なわれるのでは?という仮説の正当性は高まります。
効率化の元に情報伝達が一方通行になれば、意見を述べにくい雰囲気になる、
また、情報共有が不十分になると、ミスが発生しやすくなり、その責任追及で心理的安全性が損なわれるのではないか。
この辺りがコミュニケーション擁護派の意見になりそうです。
では、職場でのコミュニケーションは、多ければ多いほど、心理的安全性にとってよいことなのでしょうか?
多くの職場は、それぞれのメンバーが役割やスキルに応じた担当を持ち、パフォーマンスを発揮することで成り立っています。
役割に必要な情報は様々であり、一律ではありません。
マネジメントは中長期の計画や進捗、市場動向などビジネス全体を俯瞰する情報が必要なのに対し、担当者は担当業務の直近の進捗と、今週の予定がわかれば十分だったりもします。
心理的安全性を構成する要素に「無知だと思われることを恐れない」があるのはお伝えした通りですが、新しいことを学ぶ機会としてのコミュニケーションというのは、メンバーの公平感に配慮するあまり、往々にして過剰になりがちなのです。
コミュニケーション効率化の意見は以下のようなものなりそうです。
効率化によって、メンバー個々に必要な十分が迅速に共有されることで、意思決定の質が向上する。
メンバーがより創造的な業務に集中できるようになり、心理的な余裕が生まれる。
今の自分には関係ないコミュニケーションで時間を奪われているといったストレスが軽減される。
いかがでしょう?むしろ効率化した方がよいと思えてきたのではないでしょうか?
本テーマのまとめとして、コミュニケーションを通じて心理的安全性を高める為には、以下の3点が重要です。
1.内容が自分事として捉えられる範囲であること
2.上手く行くコミュニケーションであること
3.必要十分を満たした効率化がなされていること
ここまでお読みいただくと、薄々お気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、コミュニケーションは心理的安全性に影響する重要な要素ではありますが、必要十分条件ではないのです。
心理的安全性を醸成する為のコミュニケーション以外の要素としては、先に説明したリーダーシップや、組織文化、チームの構造などがあります。
これらについては、また機会を改めてご説明できればと思います。



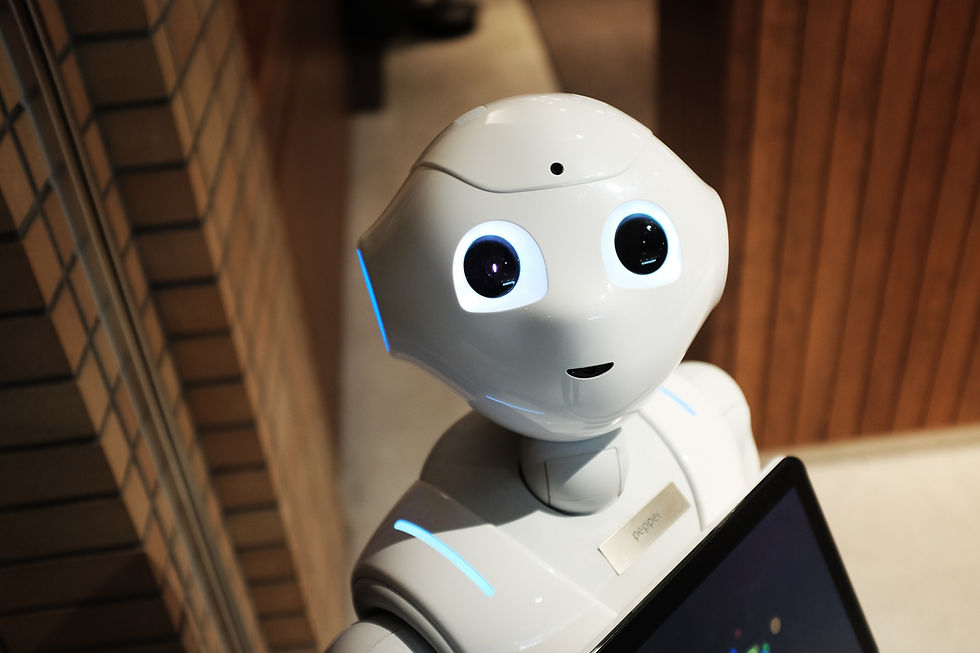
コメント